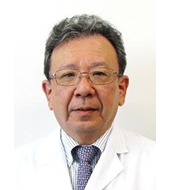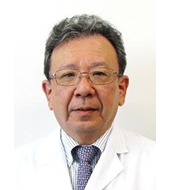センター長メッセージ
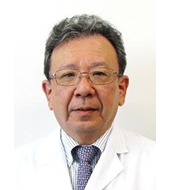 |
センター長 岩永 知秋 |
今年は異例の早い梅雨明けの後、毎日日本列島を猛暑が襲っています。九州はもちろんのこと、北海道でも30度を超えることが多く、気候変動の一端を示しているのかもしれません。近年の酷暑は、度重なる線状降水帯の発生やそれがもたらす集中豪雨などにより、これまで私たちが経験したことがないほど自然災害を発生させるに至っています。
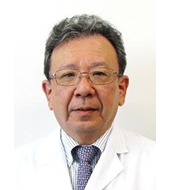 |
| センター長 岩永 知秋 |
最近の言葉として、「VUCA時代」という語が登場しています。これは変動制、不安定性、複雑性、曖昧さを意味する英単語の頭文字を連ねたもので、将来の予測が難しい状況を意味するそうです。確かに、気候変動や自然災害のほかに、グローバル化とその反動のような様々な分断、ITやAIなどの発達、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を代表とする新興感染症、国際紛争・戦争などの地政学的リスクなど、世界の変容をきたす要因は多種多様で、枚挙にいとまがありません。まさに私たちは、未来を見通すことができないほど不透明な現代を生きています。
コロナ禍が終息方向に向かう中、コロナ補助金の廃止、諸物価の高騰、人件費の上昇などから、わが国の医療機関の実に6割が昨年度赤字を計上しました。医療や福祉は、消防や警察など私たちの生活に欠かすことのできない、大切なインフラです。しかしながら、診療報酬は物価や地域差などが考慮されずに、2年に1回定期的に設定される公定価格のため、社会の変化にリアルタイムに追随できない宿命があります。久山療育園は職員の努力により何とか赤字を避けることができていますが、さらに工夫を重ねながら、重症心身障害を有する利用者のために、より良い医療、看護、介護、リハビリなどを届けて参ります。
また、最近は人材不足が社会で顕在化していますが、私たちの領域でも喫緊の課題となっています。ことに介護にあたる介護福祉士、支援員などの人材がなかなか充足されません。
全国の重症心身障害の協議会でもこのトピックについて議論が行われましたが、地域を問わず全国に共通した問題であることがわかりました。特に障害者の医療・介護は労働集約型の職務形態であり、何といってもマンパワーは貴重な宝です。アジア諸国からの外国人雇用も、すでにいろいろな施設で開始されています。その一方、日本は少子高齢化人口減少社会という特性から、今後この人手不足がさらに悪化することが懸念されます。久山療育園でもその検討に入っていますが、慎重に、しかしスピード感をもって進めていく必要があると考えています。国内外を問わず、広く、貴重な介護人材を求めています。
2023年5月にCOVID-19は感染法上の取り扱いが5類に改められ、今年初めの流行の後はある程度落ち着いた状況にあります。久山療育園でも、利用者や保護者の方々に心ならずも強いてきた諸々の制限の緩和を進めています。外出、外泊、短期入所、特別支援学校、ボランティア活動、諸行事、短期入所など、本来から言えば障害を持つ人の生活を彩る生き生きとした活動を、ようやくコロナ前の状況に近づけつつあります。今後の流行の再燃に注意を払いながらも、重症心身障害を持つ人とその周囲の方々の人生がより充実したものになるよう、職員一同心を合わせて努力して参ります。
久山療育園重症児者医療療育センターについて
久山療育園重症児者医療療育センター(「久山療育園」)は1976年9月に開園し、2008年度に「久山療育園重症児者医療療育センター」と名称を変更しました。それは、これまでの働きが創立理念に従って、進めてきた結果です。即ち「久山療育園は単なる収容施設ではなく、新しい福祉社会(福祉共同体)づくりの拠点である」という理念に基づいて、2015年7月に「在宅支援センター」が開設されました。
「在宅支援センター」の働きから福祉共同体の実現、地域医療連携へと、創立理念がようやく実現に至る端緒に着いたことになります。「在宅支援棟」の役割は、「在宅支援センター」の司令塔としての働きであり、「重症者ホームひさやま」は久山療育園の医療病床94床(①医療重点病棟、②療育重点病棟、③生活重点ユニット及び短期入所病床併設6床)へと繋がる第四の入居受皿となるグル−プホームです。これまで限界まで家庭で過ごして来られた重症心身障害児(者)とご家族の付託に応えられる「共にある」存在となれれば幸いです。